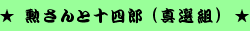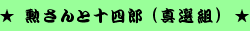□俺の太陽 ('08.8.12)
1ページ/11ページ
真っ暗な星一つ無い夜空。
空も地上も漆黒の闇の中。
それも、もう直ぐ朝日が昇り、明るく輝く新しい一日が始まる。
薄れ行く意識の中で、あの辺りが自分達真選組が護って来た大江戸の街なのだなぁと十四郎はぼんやりと眺めた。
只口に咥えたままのタバコは、灰の長さだけが伸び何時しかポロリと十四郎の膝の上に落ちる。
十四郎はやっとの事、腕を動かし懐から一枚の写真を取り出す。
薄暗いこの場所で、いかにも太陽の元で見ているかのようにニッコリと微笑んで写真を見る。
写真は昔、近藤と十四郎が武州から大江戸へ向かう前の日に撮ったものだった。
冷え切った体を昇り始めた太陽の温もりが包む。
ああ、あの人の温もりと同じだ・・・ふっと、十四郎の表情が和む。
霞んで行く視界の中で、
「近藤さん、俺はあんたの大事を護ったぜ」
静かに呟くと同時に咥えたタバコが己の流した血溜まりの中に落ち、ジュッと小さな音を立てて消えた。
そして、写真を持った手もパタリと力なく地面に落ちた。
近藤は大江戸に出て来て直ぐにお妙と巡り合った。
弟と二人健気に親の残した道場を建て直すと、夜な夜な男達に媚を売るスナックで働いていた。
近藤はそんな水商売に身を堕してもなお、自分の信念に生きるお妙に共感したのだ。
3日と空けずに近藤はお妙のスナックに通った。
帰れば、必ずお妙の事を十四郎に報告した。
近藤は親友であり優秀な片腕である十四郎に隠し事はしたくなかったのだ。
だから、毎日のように日記を書くような軽い気分で十四郎に報告するのだった。
十四郎は近藤の日課となった其の日一日の報告を黙って穏やかな微笑みを湛え聞いている。
十四郎は近藤が笑顔で幸せに暮らしてもらえればそれで良かった。
だから、"鬼の副長"と世間で揶揄され嫌われても苦痛ではなかったのだ。
近藤の笑顔で十四郎の心は癒されていたから。
十四郎は近藤の口から毎日のように聞かされる"お妙"という名の女に嫉妬は感じなかった、それよりも近藤を癒してくれるこの女性に感謝した。
十四郎は一度だけお妙に会った事がある。
近藤がお妙と出会って暫くしてから、一緒にお妙の勤め先へ飲みに行ったのだ。
お妙は十四郎の想像していた通りの女だった。
意思の強さを物語る黒目がちの瞳、綺麗に結い上げられた黒髪、ころころと鈴を転がすように響く声・・・どれも近藤の好みにぴったりだった。
この女(ひと)なら近藤を幸せにしてくれると思った。
お妙は一目十四郎を見るなり、
「こちらが、噂の土方様ですのネ。ホント、お綺麗な方ですわねぇ〜」
近藤の隣に座り、ニッコリと微笑みを十四郎に投げ掛けた。
それは営業用の取ってつけたような笑顔では無く、心の底から嬉しいと表している。
近藤はお妙の言葉に、己の頭をガシガシと掻き、
「俺の自慢の親友兼右腕ですからね」
薄暗い店内の照明ながら、今の近藤は真っ赤になって照れているのが判る。
「まっ、近藤さんたらオホホホ。何も近藤さんが照る事ありませんよ」
お妙は白く細い手を口元へ遣り笑った。
「俺はトシの事、褒められるのが一番嬉しいから」
近藤は黙って二人の遣り取りを聞いている十四郎へと顔を向け、ニッと笑った。
「馬鹿な事言ってんじゃあねぇ」
十四郎は相変わらず表情が読めない顔で、タバコに火を点けて深く吸い込み、フーッと吸い込んだ煙を吐き出した。
十四郎はこういった席は苦手だったが、近藤の脇に座りチビチビと酒を啜りながら近藤とお妙の遣り取りを聞いていた。
出会ってそう時間も経って居ないのに、二人の間には長年知り合いだったような、気さくな空気が流れている。
その時初めて十四郎は、疎外感を感じた。
二人が醸し出す恋人同士のような雰囲気に、居た堪れなくなった十四郎は酔ったからと一人席を辞して屯所へと帰った。