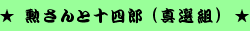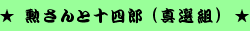□Innocent Love ('08.11.16 更新)
1ページ/13ページ
「トシ、もうこれっきりにしよう」
その言葉は唐突に近藤の口から発せられた。
言葉の意味が理解できずに十四郎は近藤の顔を凝視していた。
「俺、もうお妙さん一筋にしようと思って。お前にはすまないが別れてくれ」
たった今、交わったばかりの蒲団の上で手をついて頭を下げる近藤を只黙って見ていた。
そうだ、今夜近藤に対して感じていた違和感はこれだったんだ。
いつもよりも優しい愛撫、そして何よりも不信を感じたのは、近藤の目だった。
行為の最中、視線を感じて目を開けばそこには優しさの中に悲しさを漂わせた近藤の目があった。
いつかは、来る別れであった。
いつ来ても、近藤の幸せがあるのなら自分は黙って別れるようと覚悟していた。
それが、こんなにも早く来るとは思ってもいなかった。
「解ったよ、それでアンタが幸せになるなら・・・今までの事は忘れてくれ」
溢れそうになる涙を堪えて、脱ぎ散らかした着物を手繰り寄せ、震える手で・・・しかし、何事も無かったように平然とした顔で着物を着ると
「それじゃ、な。ありがとよ」
トシと小さく呟く近藤に、聞こえなかったように振り向くこともせず十四郎は近藤の部屋を後にした。
立っているのがやっとだった。どのようにして自分の部屋へ戻って来たのかも覚えていなかった。
十四郎は出会ってからずっと近藤を愛して来た。
あの、お妙の代わりと知りつつも近藤の求めに応じて体を開いて来た。
・・・お前とお妙さんと二股かけてちゃぁ、お妙さんも本気になっちゃぁくれねぇだろう。だから俺はお前と別れる決心をした。だが、トシ、お前は俺の片腕として今まで通り傍に居てくれ・・・
近藤の言葉が頭の中に蘇って来た。
崩れるようにその場に座りこみ両腕で自分を抱きしめた。
こみ上げる悲しみに声を殺して泣いた。
近藤は副長として傍に居てくれと言った、しかし自信がなかった。
傍にいて、近藤の幸せを見守る事が出来るだろか?・・・きっと、自分は嫉妬に狂ってしまうのではないだろうか
自分はそんなに心の広い男ではない、なによりずっと近藤だけを見て来たのだから。
誰に何を言われ疎まれようと、近藤の存在が心の支えだった。
只の親友だったら、それも可能だったろう、だが今は自分の体が近藤を知っている。
近藤は只欲望のはけ口として自分を利用したのだろが、それでも幸せだった。
近藤に触れら、その時は近藤を独り占めにする事が出来たから、その時だけ近藤は自分の事だけを考えてくれるのだから。
でも、それももうお終いだ。
近藤から別れを告げられた、そして自分はそれを受け入れたのだから。
そして、その夜から十四郎の姿は屯所から消えた。
翌朝、近藤は慌てふためく山崎に起こされた。
何事かと問えば、一通の封筒を渡された
今朝、一番に報告しなければならない事があって副長室を訪れたが、返事が無いので部屋に入ったら机の上にこれがあったのだと。
近藤は、寝巻きのまま前が肌蹴るのも気にせず十四郎の部屋に急いだ。
勢い良く障子を開けると、やはり其処にはこの部屋の主の姿は無かった。
部屋の中はきちんと整理されて、十四郎の愛刀と身の回りの物が無く、壁には隊服が掛けてあり、机の上には隊から支給された携帯電話が置かれてあった。
山崎から渡された封書表書きには『退職願い』と十四郎特有の綺麗な筆跡で書かれてあり、なかの書面は型通りの退職願いの文書だけが書かれてあった。
「トシ・・・、何故・・・」
思わず近藤はその退職願いを震える手で握り潰してしまった。
「局長、どうしましょう・・・」
山崎はオロオロと近藤の様子を窺いながら聞いて来た。
暫く沈黙が流れて、
「山崎、トシは今日から体調不良の為、無期限の休暇だ。いな!」
普段の近藤からは想像も出来ない程の強い口調で山崎に念を押した。
「は、はい」
戸惑いながらも承知する山崎の背後から声がした
「なに、二人でこそこそ話してんですかぃ」
なかなか、食堂に姿を見せない局長と副長を呼びに総悟が出て来た。
「おお、総悟。良い所に来たな、トシは暫く休暇だ。お前副長代理をやれ」
「なんですかぃ、副長代理って。土方の野郎が又なにかやらかしたんですかぃ」
「まっ、理由はおいおい話すからな。いいな総悟」
いつになくきつい口調で有無を言わせない様子の近藤と、その後から恐る恐る総悟を見る山崎を見て何かあったと直感した総悟は
「訳わかんねぇけどついでに、その代理って言うの外してもいいですかぃ。で、土方の野郎はどうしたんでぇ」
近藤の横をすり抜けて副長室に入ろうとする総悟を近藤が制して
「トシ、まだ寝てる。いいか総悟・・・暫くは代理だ。代理」
近藤は後手でピシャッと障子を閉めながら、総悟に念を押した。
「ちっ、近藤さんの言いつけじゃ仕方ありませんゃ」
と渋々承知した、後で山崎を痛めつけりゃぁ判るかぁと目を山崎に向けると、その殺気に気づいた山崎の背中に一筋の汗が流れた。